科学研究の資金調達は深刻な課題を抱えています。暗号資産はこうした問題を解決できるのでしょうか。
7か月――これは、多くの人が結婚式の準備に費やす時間よりも長く、しかも、経験するストレスはそれ以上かもしれません。彼女はがん治療法の研究に従事する優秀な研究者ですが、実際の科学的活動よりも、資金調達のために奔走する時間の方が長くなってしまいました。
この仕組みは本末転倒です。研究には資金が不可欠ですが、資金を得るためには、その研究が成功することを証明しなければなりません。しかし、実際に研究を始めなければ、それを証明することはできません。
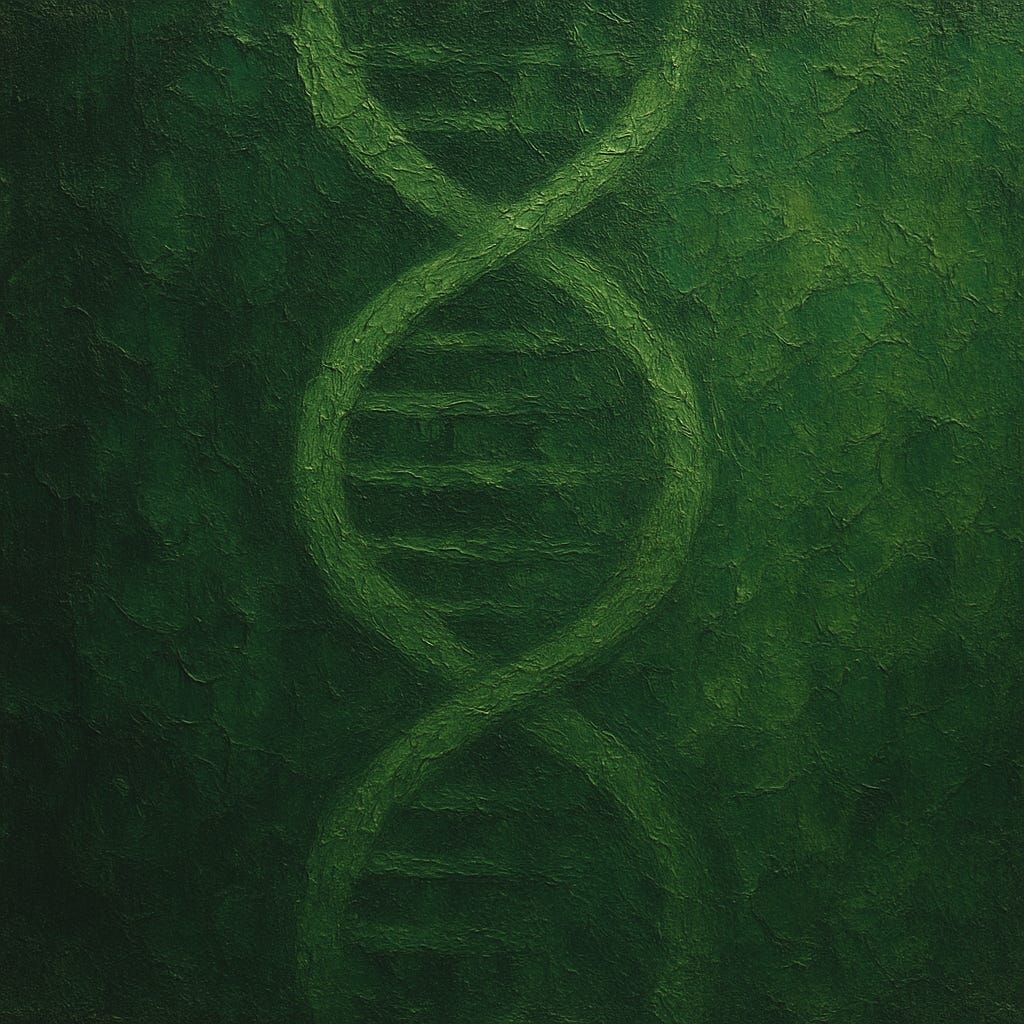
一方で、米の粒を数えるだけのYouTuberがクラウドファンディングによって週末に10万ドル(約1,500万円以上)を集める現象が存在します。このギャップは驚異的です。
暗号資産業界では今、「DeSci(分散型科学)」という新たなムーブメントが広がりつつあり、暗号資産やブロックチェーン技術を活用して科学研究の資金調達の構造そのものを変えようとしています。
先入観を持たずに、少しだけ耳を傾けてほしい――これは現実的な解決策となり得る可能性があります。
現行制度の問題点を整理します。従来の科学研究資金の流れは、研究者が綿密な提案書を作成し、政府機関や企業へ提出。その後、6~18カ月の審査期間を経て採否が決まるというものです。大半の提案は却下され、承認されても多くの条件が課され、研究者は本来の研究よりも事務作業に追われがちです。
この仕組みはリスクを最小化するために設計されています。しかし、イノベーションに不可欠なのは本質的なリスクです。抗生物質やインターネットといった画期的な発明は、助成金審査会が事前に認めないような意外性のある発想から生まれています。
さらに、「論文出版」の問題も顕在化しています。研究者は高額な学術誌に発表費用を支払い、成果はペイウォール(有料壁)の裏側に隠されます。納税者による資金で生まれた研究成果が、納税者本人の手に届かないという現状です。
結果として、優秀な研究者は何年も書類の山に悩まされ、真の課題解決が後回しになります。重要な研究が遅れたり、そもそも実現しなかったりします。そして、基礎研究の大部分を税金で支えている市民は、自らが負担した発見の果実から締め出されてしまいます。
ここで「分散型科学」の登場です。
DeSciとは、暗号資産の仕組みを科学研究に適用するアプローチです。研究者は助成金委員会に依存せず、自らの研究に関心を寄せる人々から直接クラウドファンディングで資金を集めることができます。研究成果はペイウォールの裏側ではなく、誰もがアクセスできるパブリックなブロックチェーンに公開されます。
このアイデアは、Ethereum共同創設者Vitalik Buterin氏と元Binance CEO Changpeng Zhao氏がカンファレンスで議論したことで、一気に注目を集めました。暗号資産業界の主要人物が関心を示すタイミングは、基盤技術が社会実装可能な段階に到達している証拠でもあります。
具体的な仕組みはこうです。研究者は自身のプロジェクトを表すトークンを発行し、支援者はそのトークンを購入することで研究資金が集まります。研究が成功し、商業的発見につながれば、トークン保有者はその成果利益を分配されます。
これはもはや理論段階ではありません。分散型科学向けの本格的なインフラを構築する企業が、次々と実際に現れています。
代表例の一つがBIO Protocolです。旧Binance Labsの出資を受けており、強力な資金力があります。BIOは「BioDAO」と呼ばれる投資クラブをつくり、バイオテクノロジー研究の資金をクラウドファンディングで集めます。従来のように富裕層が一部のみ研究方針を決めるのではなく、何千人もの参加者が資金を出し合い、共同で研究開発の方向性を決定できます。
MoleculeやVitaDAOは特に「長寿研究」に特化。知的財産権をトークン化し、発見があれば所有権は資金支援者全員に分配されます。現時点では、ニューカッスル大学の老化研究やコペンハーゲン大学の長寿研究などが具体的な事例です。
資金調達規模も目覚ましい伸びを見せています。これらのプラットフォームは数百万ドル単位の研究資金を扱い、個別プロジェクトでも数十万ドル相当がトークン販売によって集まっています。従来型の資金調達と比べるとまだ小規模ですが、急速に成長中です。
DeSciについて考察するほど、その必然性が明らかになります。科学は本来、協調的に発展してきました。研究者は互いの業績を土台とし、データを共有し、査読によって成果を検証します。ブロックチェーン技術は、まさに透明性と協調性のために設計された仕組みです。
従来型資金調達では、研究者は助成金獲得のため「確実性」を過度に強調しなければならず、未知で革新的なテーマの探究が妨げられます。DeSciはこの構造を転換し、あらゆるデータ(失敗例も含め)を共有することで、他者の新たな挑戦やミス回避を促進します。
さらに、グローバルアクセスも大きな利点です。ナイジェリアの研究者が革新的なアイデアを持っていた場合でも、欧米の大学や助成機関との人脈を持たずとも、世界中から資金を集めることができます。これは科学の民主化に直結する進展です。
透明性も抜群です。ブロックチェーン上のトークンで研究資金を集めれば、その用途はすべて公開され、資金が本当に研究活動に使われているかどうかを誰でも確認できます。事務経費への流用などの不透明性は払拭されます。
もちろん、課題も存在します。最大の問題は品質管理です。従来の査読制度には欠点もありますが、一定の粗悪な研究は排除できます。分散型システムでは、明らかに非科学的なプロジェクトへの資金流入をどう防ぐかが課題です。
資金の価格変動リスクも無視できません。5年規模のがん研究プロジェクトで、資金源が暗号資産トークンだった場合、トークン価格が90%急落したらどうなるでしょうか。長期研究には安定した資金フローが不可欠です。
規制も不透明です。多くの国では医薬品研究や知的財産権の取り扱いに厳格な法律があり、トークン化研究が既存の法制度にどのように適応するかは明確ではありません。
正直なところ、ほとんどの科学者は暗号資産分野の知識が希薄です。研究者にトークノミクスやDAO運営の専門家になることを求めるのは大きなハードルです。
それでもなお、DeSciは着実に動き出しています。インフラは進化し、資金調達規模も拡大。従来型の科学資金調達は煩雑さが増す一方です。助成機関が緊急研究に18カ月かけるのに対し、暗号資産クラウドファンディングなら数日で資金調達が可能です。この効率差は歴然としています。
現時点ではバイオテクノロジーや長寿研究が中心ですが、それは収益性の明瞭さが背景にあります。新薬開発に資金を提供することで、トークン保有者がその利益の一部を受け取れるのです。しかし、価値創出に繋がる研究なら、どんな分野でも応用可能です。
今は「大きな変革」の初動段階にあると考えています。暗号資産がすぐに従来の科学資金調達を完全に代替するわけではありませんが、より迅速かつ透明性が高く、世界中の研究者への開かれた選択肢を提供することができます。
真価が問われるのは、DeSciプロジェクトが本当に科学的ブレイクスルーを生み出せるか――単なる資金集めだけで終わらないかどうかです。しかし、従来制度の現状を鑑みれば、新しいアプローチにチャレンジする価値は十分にあります。
次に私が取り組むこと
まだ始まったばかりです。DeSci領域は、驚異的なスピードで変化しており、絶えず新規プロジェクトが誕生し、実際の研究現場へ資金が流れ込んでいます。暗号資産と科学資金調達が交差することで、1年前には存在しなかった新たな可能性が生まれています。
この分野を今後数週間かけて徹底的に調査するつもりです。どのプロジェクトが実際に成果を上げているのか、資金はどのように流れているのか、それが実際の科学的進展に結びついているのかを見極めたいと思っています。今やAIによる創薬から分散型健康記録まで、数十件のDeSciプロジェクトが存在しますが、その多くはまだ周知されていません。
もし、テクノロジーが社会の根幹を担う――人類の進歩を支える研究資金の仕組み――の課題解決に貢献できるかに興味がある方は、ぜひご期待ください。これから、ブロックチェーン技術にとって最重要となる応用分野を探っていきます。
科学を、すべての人にとってより良いものへ――その実現に向かってLFG!!! 🚀
免責事項:
- 本記事は[Buttercup Network]より転載したものです。著作権は原著者[Thejaswini M A]に帰属します。転載についてご異議がある場合はGate Learnチームまでご連絡ください。速やかに対応いたします。
- 免責事項:本記事の見解・意見は著者個人によるもので、投資助言を構成するものではありません。
- 本記事の他言語翻訳はGate Learnチームが担当しています。特記がない限り、翻訳記事の転載・配布・盗用は禁じます。
関連記事


ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて

